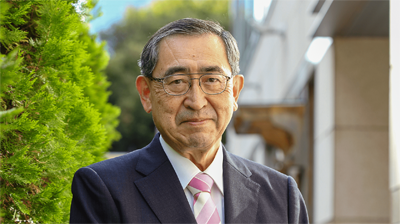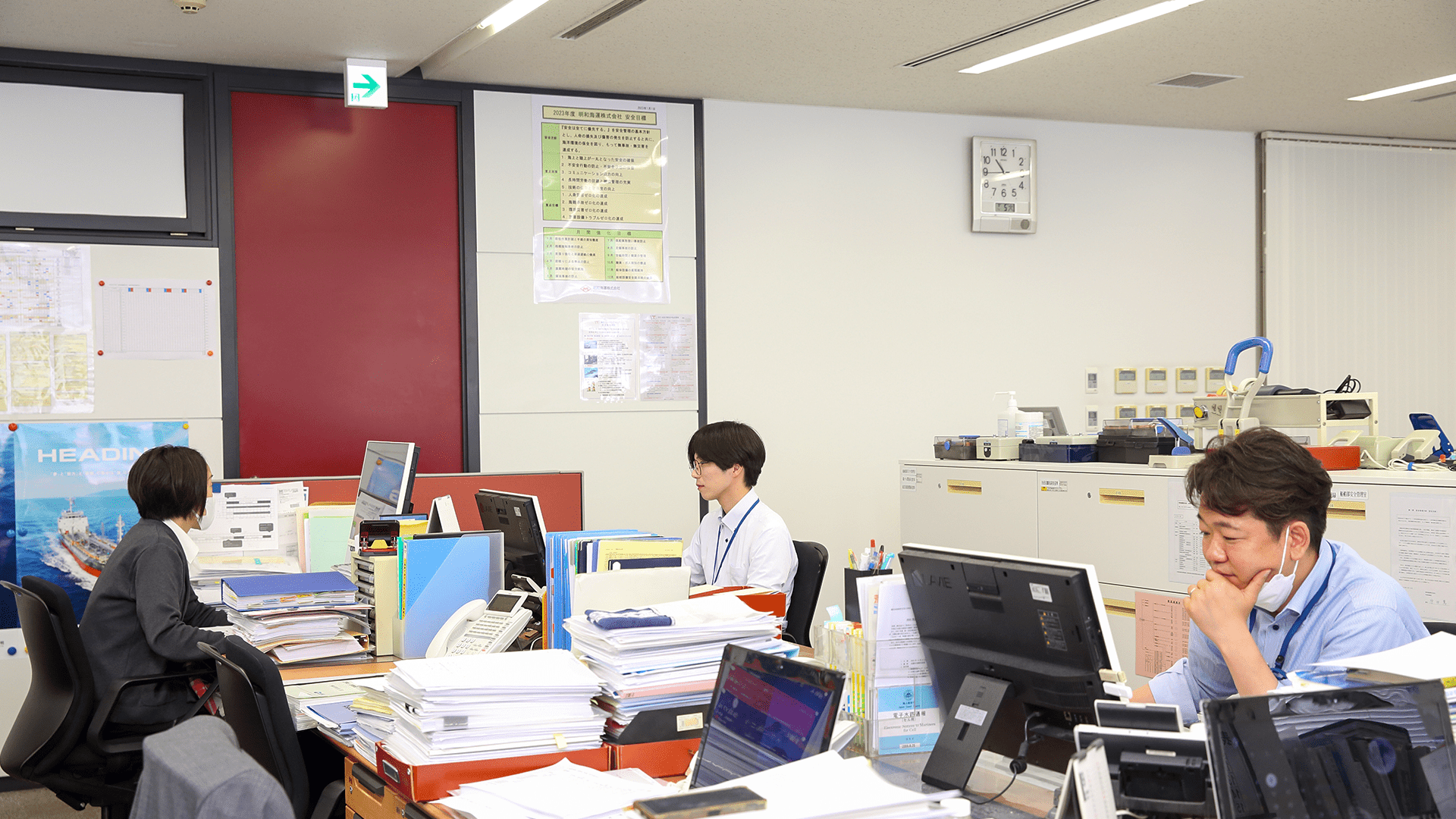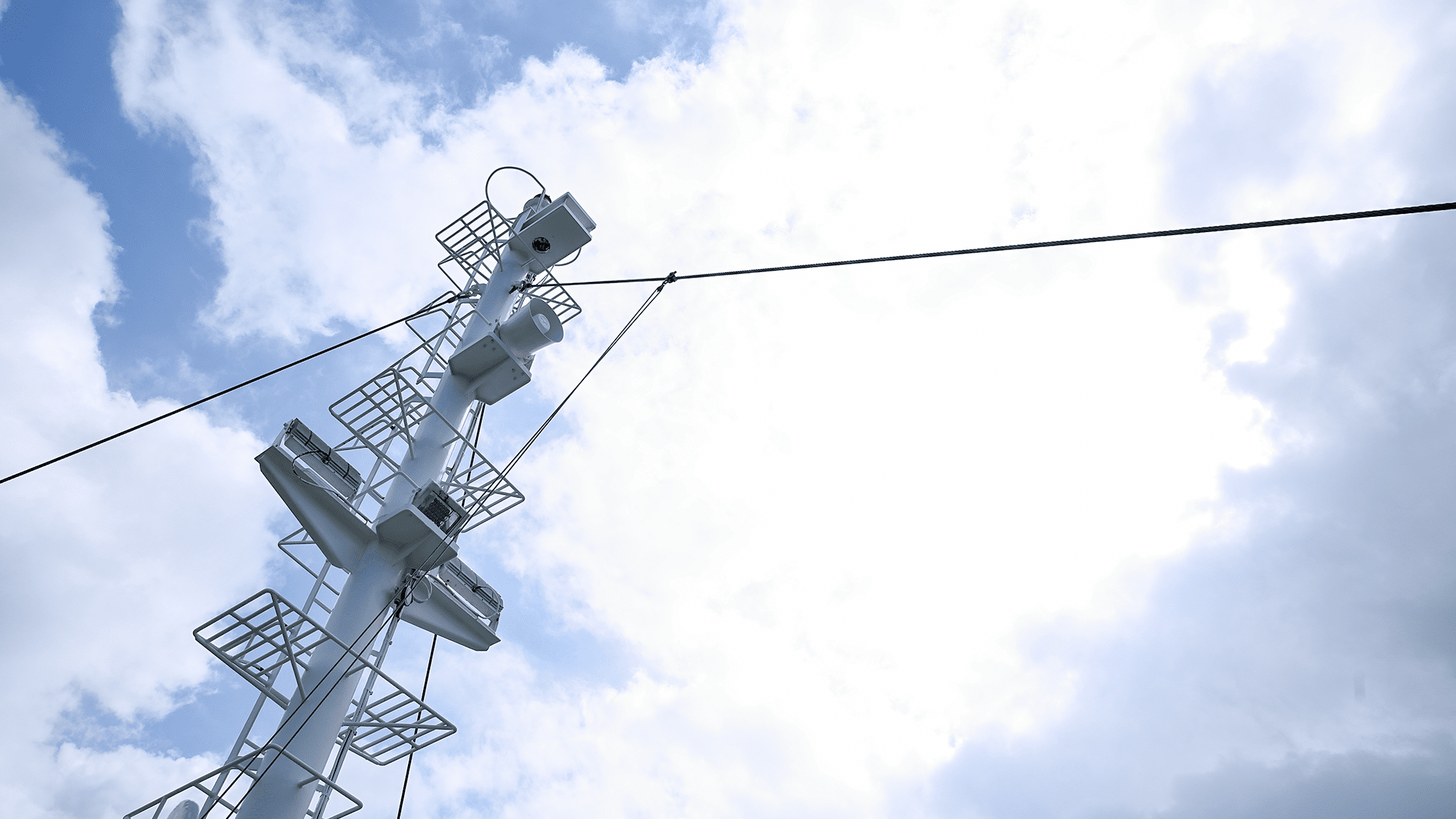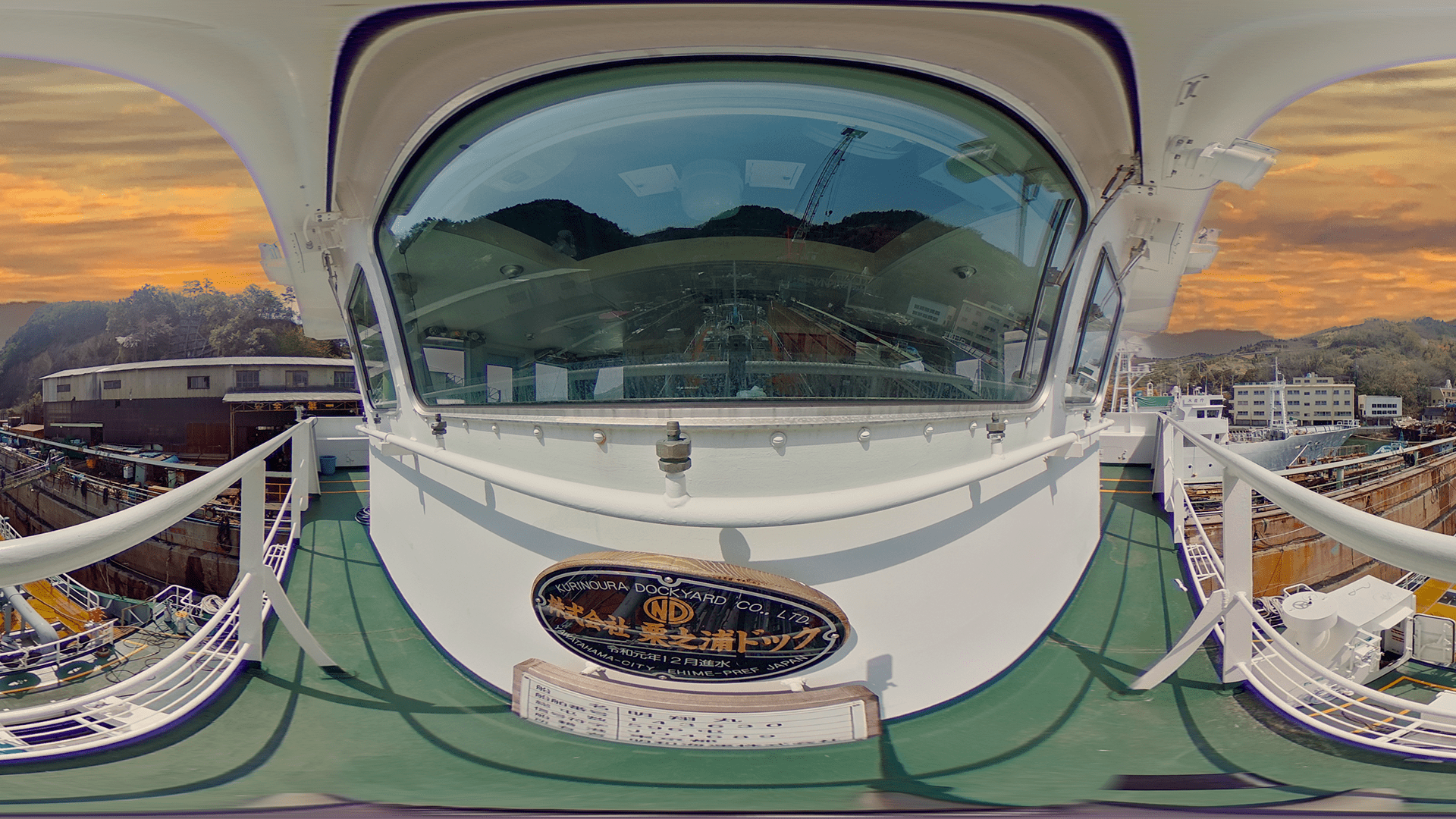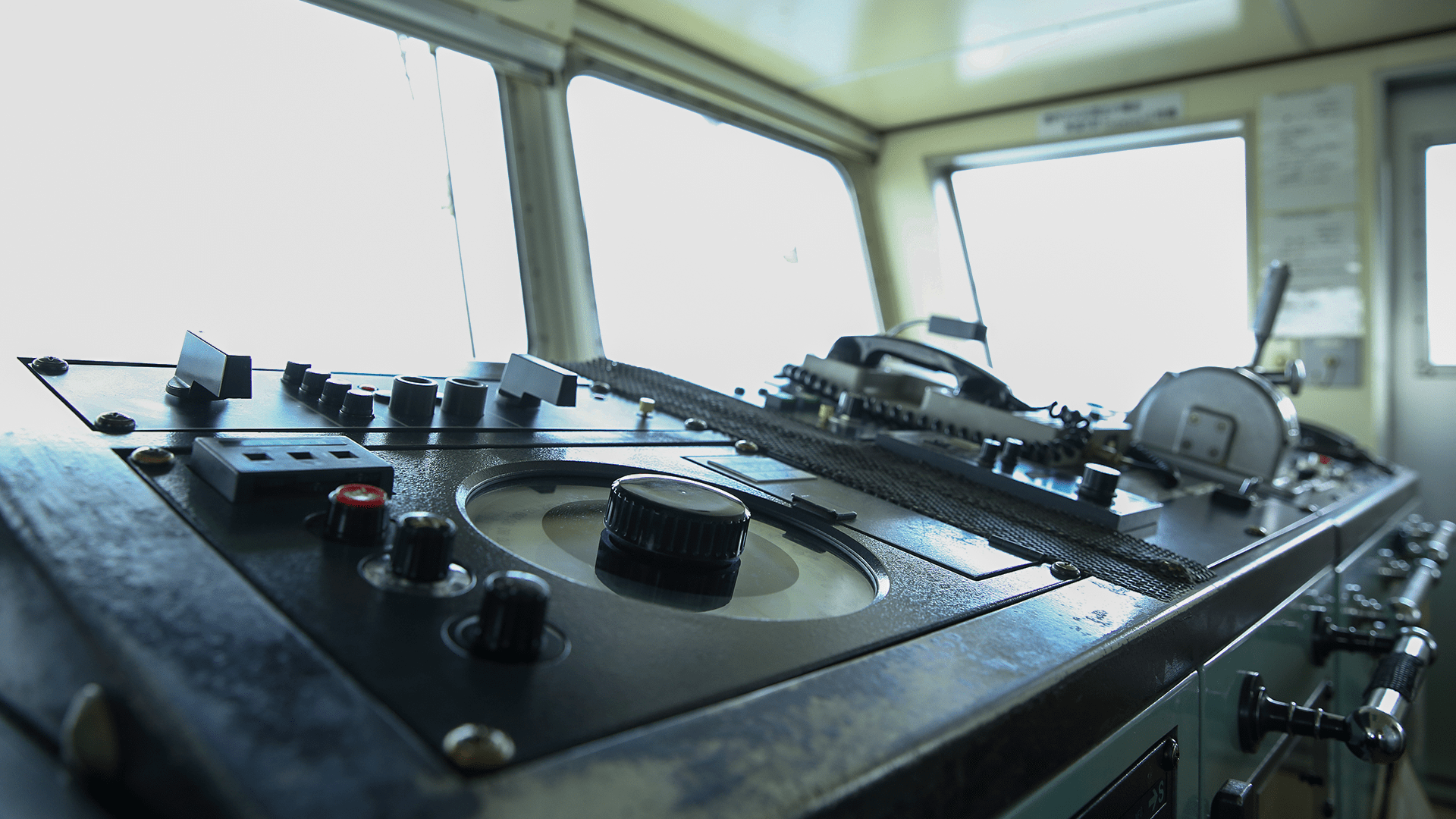海運豆辞典
船名の「丸」の由来
船の船首と船尾には船名が表示されており、会社名、地名や都市名をそのまま名付け
たりするなど様々あります。日本の船は昔から船名に「丸」を付けることが多く、平安時代の書物の中に坂東丸(ばんどうまる)という船名が出てきています。
なぜ「丸」を船名に付けるようになったのかは諸説ありますが、最も代表的なものは「麻呂・麿(まろ)」が「丸」に変化して付けられるようになったという説です。平安時代から自分のことを「麻呂・麿(まろ)」と呼んでいたのが、のちに「柿本人麻呂(かきのもとのひとまろ)」のように敬愛の意味で人に付けられるようになり、飼っている犬や刀などの大切なものや愛するものにも付けられるようになり、さらには船にも付けられるようになりました。その後、「麻呂・麿(まろ)」が「丸」に変化していきました。
もうひとつは、「本丸」「一の丸」といった城の構造物を呼ぶ時の「丸」から由来する説です。「本丸」「一の丸」の「丸」は大小便を意味する「放る(まる)」が由来であり、現在でも小さい子供が使う持ち運び式の便器を「おまる」と呼ばれています。わざと忌み嫌われる名前を付けることにより、災いを払う意味が込められています。その魔除けを願う風習から、城だけでなく、男の子の名前や船にも「丸」と付けるようになったとも云われています。

本文出展:「株式会社ポートサービス」
https://www.portservice.jp/businessblog/trafficboat/2022071930.html